2023年石川県での地震や京都での大雪、千葉地震や、
ヒョウの災害などで税金の問い合わせがありましたので書いていきます。
2019年9月、首都圏に巨大な台風15号が上陸し、
千葉県を中心に甚大な被害をもたらしました。
大規模停電も引き起こし、
家屋の損壊は2万戸にも上り、
今なお復旧が進んでいない家屋もあるほどです。
このような自然災害による被害を補償してくれるのが、火災保険です。
台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。
保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。
それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる
申請主義だからです。
現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが
保険金が降ります!!自信あります。
【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】
※被害自覚なくても無料点検オススメします
2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。
災害が来る前に大事な建物を点検させてください。
【問い合わせ】

目次
火災保険は万能な保証がついています

火災保険という名称のおかげで、
火事による被害だけを補償すると思われがちな損害保険ですが、
基本補償に
台風や大雨、
落雷による被害を補償する項目が入っていることがほとんどです。
そして、特約を加えると、漏水事故や盗難など偶発的・突発的な事故の被害も補償できるようになります。
とはいえ、日本は自然災害大国ですので、
いつどのタイミングで自分も被災するかわかりません。
そして、被災して火災保険を活用した際には、保険金は課税対象になるのでしょうか。
今回は、火災保険と税金にまつわるあれこれをまとめて紹介していきます。
火災保険が値上げされている背景
実は、火災保険の保険料は一定ではなく、
価格が変わるタイミングというものがあります。
2019年10月の価格改定では、基本的に値上がりする物件が多くなりました。
これは、保険会社のプランの内容によって、その多くが値上がりしたのですが、
一部地域や建築部材・構造により値下がりしたケースもあるため、
「基本的に」値上がりとなったわけです。
今回の改定で、保険料が倍以上になったケースもあれば、
変化なしのケース、値下がりになったケースなどさまざまです。
火災保険は商品によってかなり内容がかわるため、
このような価格の変化が起こるというわけです。
今回の保険料の変化の骨子は、
保険会社各社が保険料改定の目安とする
「参考純率」が、全国平均で5.5%引き上げられことがポイントとなっています。
その背景には、日本全国で自然災害が増加し、火災保険の活用件数が増えたからです。
火災保険金の原資は、各保険会社の利益です。
そのため、利益を多く確保しておくためには、保険料を上げるしかありません。
(その他企業努力があるのでは?という観点はここでは除いておきます)
2019年の千葉の惨状や、毎年各地で発生する台風や大雨による被害を見ると、
いつどのタイミングで自然災害の被害に遭うかわかりません。
そのため、火災保険の必要性が見直され、
加入世帯も増えているという現状があります。
そして、安心できる補償を受けるためには、それなりに保険料は高くなってしまいますので、
ライフプランにも影響が出てきます。

火災保険の控除について
では、火災保険に加入した場合は、
年末調整や確定申告などで控除を受けられるのでしょうか。
生命保険の場合は、毎年保険会社から
「生命保険料控除証明書」が郵送されてきていると思いますが、
保険料の一部が控除されることになっています。火災保険も同じ保険ですので、
控除の対象になるのでは?と思うかもしれませんが、残念ながら2007年以降対象から外れてしまいました。

しかし、生命保険以外には
「公的年金」
「健康保険」
「介護保険」などの社会保険料と、
「地震保険」は控除対象となっています。

保険料控除の対象になるのは、
生命保険・社会保険・地震保険の3種類のみとなっていますので、
自動車保険や旅行保険、そして火災保険などは対象外となっています。
地震保険料の控除については、所得税の控除額は最高で5万円です。
年間の保険料が5万円以下の場合は、全額が控除されます。
ちなみに、火災保険では地震・噴火・津波による被害は補償されないので、
火災保険とセットで地震保険に加入することで補償対象にできます。
つまり、あらゆる自然災害に備えて火災保険・地震保険をセットで加入した場合は、
火災保険料は控除されず、地震保険料だけが控除されるというわけです。

このような不公平感が出るのはちょっと変に思うかもしれませんが、
地震保険はほかの損害保険と性質が大きく違います。
地震保険は単独で加入できず、
火災保険の特約のような位置づけで加入することになりますが、
実はどの保険会社で加入しても、
同一条件の下では補償内容も保険料も同じです。
しかも、民間の保険会社だけではなく、
国も運営に参加している「半官半民」の保険ですので、
保険会社の利益は考慮されず、被災者の生活の立て直しのために活用される保険となっています。
火災保険金が下りたときは課税される?

火災保険金は、被害の状況にもよりますが、
年千万円というような大金が下りるケースも少なくありません。
そのような場合、その保険金には税金はかかるのでしょうか。
まず火災保険ですが、基本的な補償のほかにもさまざまな特約がありますが、
地震保険も含めて、その保険金には課税されません。
火災保険・地震保険に加え、公的な支援金なども、
災害からの復旧及び生活の再建を図るのが目的となり、
利益は発生しないものと考えられるので、非課税となっています。
※一部個人ではなく会社としてもらった場合には税がかかる場合もあります。

保険金では賄えないレベルの大被害が発生したときはどうする?
では、火災保険金・地震保険金が振り込まれたとしても、
それだけでは被害のすべてを修復できない場合や、
そもそもそれらの保険に未加入だった場合は、
もうどうしようもできないのでしょうか。
実は、そのようなケースでも活用できる所得税の減免及び軽減の仕組みというものがあります。
これは、所特税法上の「雑損控除」と、
税法とは異なる「災害減免法」の適用の2つで、
どちらか有利な方をセレクトして申請します。
まず雑損控除ですが、これは、火災や自然災害のほかにも害虫被害や盗難などで、
所有している資産が被害を受けたときに、
税金の計算をするときのベースとなる所得から一定金額を控除することで、
所得税を減額できるという制度です。
対象となるのは、
日常生活に必要な住宅・家財・自動車などで、
事業用の資産及び一般的な生活には必ずしも必要ではない別荘やゴルフ会員権などは対象外となります。

雑損控除額の計算については、
対象となる住宅・家財の被害額に、
災害関連支出(災害が終わった日から1年以内に支払った原状回復費用や被害拡大を防止するための費用の総額)の金額を加え、
そこから受け取った保険金を差し引いた
「差し引き損失額」をベースにします。
具体的には以下の通りです。
① 差し引き損失額-所得金額の10分の1
② 差し引き損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
このいずれか多い方の金額が適用され、
その年の所得金額から控除されます。
ちなみに1年では控除できないほど損失が大きい場合は、
3年間に渡り損失額の繰り越しが可能です。
この控除を受けるためには、
納税者本人が確定申告をする必要があるため、
サラリーマンの年末調整では控除されないことを覚えておきましょう。
続いて、災害減免法の適用については、
被害の原因が自然災害に限られていて、
所得が1000万円以下の人が対象となります。
差し引き損失額が、住宅・家財の時価の50%以上であることも要件となります。
所得税の減免額については、以下の通り定められています。
① 所得金額の合計額が500万円の場合…全額免除
② 同じく500万円超750万円以下…50%が免除
③ 同じく750万円超1000万円以下…25%が免除

この災害減免法を利用するためには、
雑損控除と同じく確定申告が必要ですので、年末調整だけでは控除されません。
また、雑損控除と違い損失額を翌年以降に繰り越すことはできないことを覚えておきましょう。
雑損控除と災害減免法のどちらが有利なのかは、被害の状況や所得などにより変わってきます。
年間所得額を上回るような被害の場合は、損失を繰り越せる雑損所得が良いでしょうし、
災害減免法の場合は所得を一気に減額できることもあります。
被害を受けたとしても、冷静に損をしない制度を活用しましょう。
事業者の税金について
では、事業用の火災保険に加入している場合、
事業に関わる建物などが被害を受けたときの損害保険はどのような税金がかかるのでしょうか。
それは、保険料を支払っているのが法人か個人事業かで違いがあります。
個人が支払っている場合の事業用の火災保険は、
一般の火災保険と同じく保険金には課税されません。
つまり、この保険金に関する税務申告も不要となります。
しかし、事業用の建物の修理にかかったコストが、
支払われた保険金の範囲内だった場合は、
それを修繕費として計上して控除を受けることはできないので注意しましょう。
一方、保険金を上回る修繕費となった場合は、その超えた分(自己負担した分)を経費として処理できます。
また、法人が保険料を負担している場合は、
支払われた保険金は法人の収入になるため、
修繕費などのコストを経費計上し、
保険金から相殺する形で処理します。
もし、コストが保険金の範囲内で収まり、余剰の保険金が発生した場合は、
収入として課税されます。
具体的な損害保険の処理方法
個人事業主が加入する損害保険には、
どのようなものがあるのでしょうか。
そもそも損害保険とは、自然災害や怪我、盗難などの偶発的・突発的な被害が発生したときに、
その損失を補償してもらうために加入する保険で、
火災保険・傷害保険・自賠責保険などがあります。
損害保険は、実際に被った損失額を実額で受け取れることが特徴で、
万が一大きな被害が発生したとしても、
事業活動の継続のための資金が補償されます。
基本的には、一定の掛け金を保険会社に定期的に支払うことになりますので、
以下のような経理的な処理を行います。
●損害保険料を支払った場合の処理方法
では、個人事業主が損害保険の掛け金を支払った場合はどのような処理をすれば良いのでしょうか。
損害保険料を支払った場合の会計処理では、
経費になるものと経費にならないものがあることに注意が必要です。
というのも、経費になる損害保険料は、
事業に関係のあるものだけなので、
店舗や商品に対する火災保険・地震保険などは経費として計上できますが、
居住用の建物・家財の火災保険や、
個人事業主本人の傷害保険など事業に直接的に関係しないものは経費にはできないことを覚えておきましょう。
具体的には、以下のようになります。
※店舗に対する火災保険料1万円を事業用の普通預金から支払った場合借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要損害保険料 1万円 普通預金 1万円 火災保険料
損害保険料は、
経費科目の「損害保険料」で処理します。
経費にならない損害保険料の支払いについては、
仕訳不要となりますので記載しません。
●損害保険金を受け取った場合の処理方法
個人事業主が損害保険金を受け取った場合は、
受け取った損害保険金が非課税のものであれば経費も非課税で処理しますし、
損害保険金が課税であれば経費も課税で処理します。
しかしながら、受け取った損害保険金が
非課税の場合でも、損害保険金よりも損失が大きかった場合は課税で処理することになります。
例えば、3000万円の店舗が焼失したとして、
2000万円の損害保険金を受け取った場合は、
建物の被害が損害保険金を1000万円も超えています。この場合は、
受け取った損害保険金を超える損失分にあたる1000万円を経費として計上できます。
具体的には以下の通りです。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要事業主貸 2000万円 建物 3000万円 火災により建物焼失雑損失 1000万円 火災により建物焼失
雑損失の代わりに「雑費」などの経費科目で処理しても問題はありません。
ちなみに、地震保険の補償は居住用の建物・家財に限定されていますので、
法人向けの火災保険の特約で加入することになります。
ちなみに、被害が甚大だった場合は納税ができるレベルではない状況になってしまうこともあるでしょう。
この場合は、税務申告や納税において、
大型災害などの際に納税期限の猶予や納税額の減額が認められる制度があるので、
税務署や税理士に相談してみましょう。
被災しただけでも計贅的なリスクが発生するのに、
さらに税金を滞納してしまうとどんどん問題が大きくなってしまいます。
このケースにおいては、救済措置となる制度を有効に活用しましょう。
災害リスクを考慮して計画的な保険の加入を

このように、日本に住んでいる以上は自然災害による被害を受けるリスクは誰にでもあります。
被災したときに、少しでも早く日常生活を取り戻したり、事業を再開させたりするためには、
火災保険を上手に活用すべきです。
そして、その火災保険と税金の関係を知っておくことも大切なポイントです。
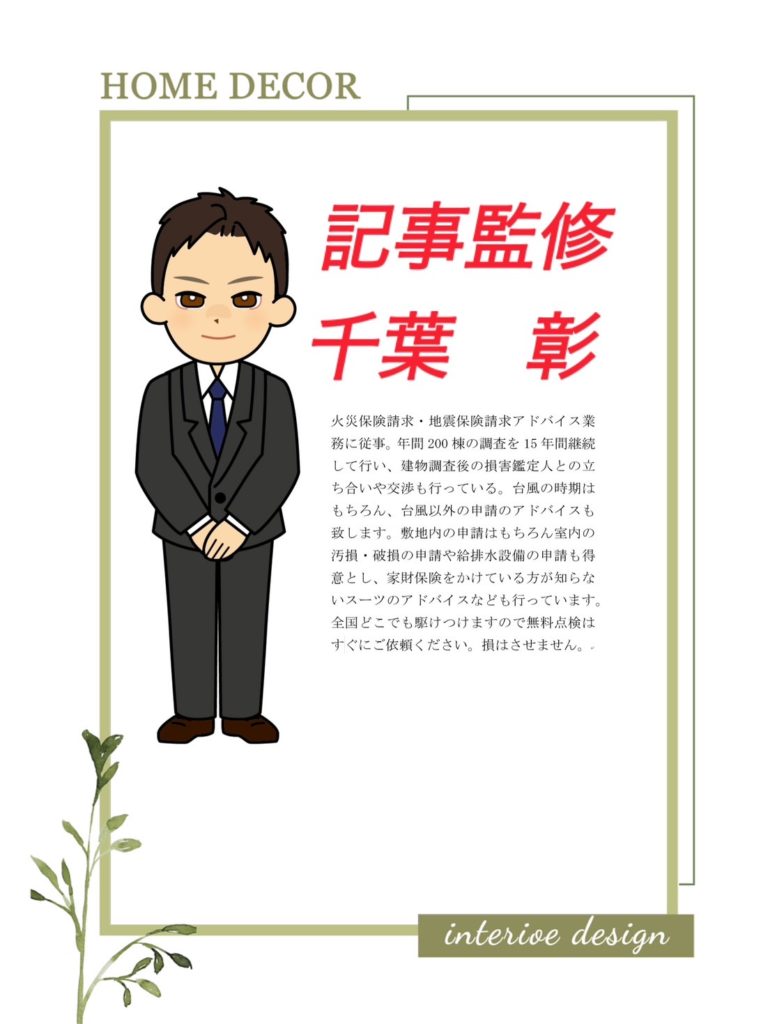
| 【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |
| 名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ! でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |



