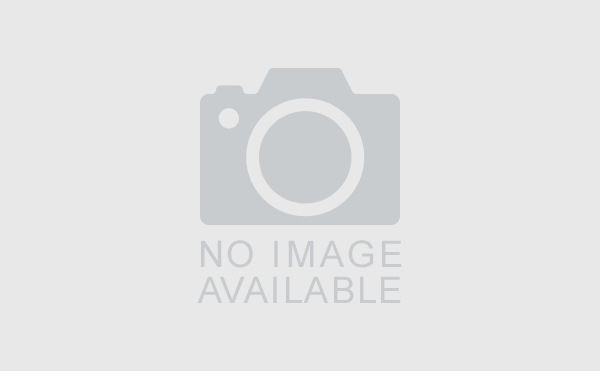目次
地震のクラックとは
地震のクラックとは、
地震発生時に地表面や地下に生じる亀裂や割れ目のことを指します。
地震は地震波と呼ばれる振動を生じるため、
地表面や地下の岩盤が強い力を受けて変形し、クラックが発生することがあります。
地震のクラックは、地震の大きさや発生場所によってさまざまな形態を示します。
小規模な地震では、地表面に細かい亀裂が生じることがありますが、
大規模な地震では数メートル以上の大きな割れ目が生じることもあります。
地震のクラックは、地震が発生した場所の地質構造によっても異なります。
たとえば、断層帯と呼ばれる地下の岩盤がずれる箇所では、
長いクラックが生じることがあります。
また、地下水や液状化現象が生じた場所では、地盤沈下や大きな亀裂が生じることがあります。
地震でクラックが入りやすい箇所
地震が起こると、クラックが入りやすい場所には以下のようなものがあります。
1.断層帯
地震の発生は、地下の断層帯で岩盤がずれることが原因の一つです。
断層帯には、活断層と非活断層がありますが、特に活断層に沿って建物が建っている場合はクラックが入りやすくなります。
2.液状化現象が起こりやすい場所
地震が発生すると、
地下水や地盤の砂が液状化して、地盤が沈下したり、大きなクラックが入ったりすることがあります。液状化現象が起こりやすい場所は、
主に河川の周辺や海岸部、湖沼周辺など、地盤が砂や泥の地域が挙げられます。
3.地盤が軟弱な場所
地盤が軟らかい場所では、
地震によって地盤の沈下や崩落が起こることがあります。例えば、干拓地や埋立地、沼地などは、地盤が軟弱で地震による被害が大きくなる傾向があります。
4.建物や構造物の基礎が不十分な場所
地震によって建物や構造物が揺れた際、基礎が不十分だと建物の崩壊やクラックの発生が起こりやすくなります。特に、地盤が軟弱な場所や、河川や湖沼周辺の土砂の堆積がある場所では、基礎の強度が不十分だと被害が拡大することがあります。
これらのような場所では、地震による被害が大きくなる可能性があります。
地震対策を行う場合には、これらの要因を考慮して建物の耐震設計や、
土木構造物の安全性の確保が必要です。
地震保険料は築年数によって変わる!地震保険の割引制度
地震保険は、国と保険会社が共同で提供しているため、
月々の保険料は、どの地震保険でも一律です。
ただし、保険商品ごとに保険料の違いはないのですが、
建物の築年数や地域によって保険料が変わる場合はあります。
一般的に、地震のリスクが高いといわれる地域では、保険料も高くなってしまいます。
一方で、築年数に関しては、
「築年数が古いと地震保険の保険料が高くなる」というわけではありません。
しかし、築年数が古いと保険料の割引制度が利用できないこともあるので、
結果的に、新しい家のほうが保険料は安くなるといえるでしょう。
建築年割引について
建築年割引は地震保険に加入する際に受けられる割引の一つとなります。「昭和56年6月1日以降」に建てられた家が対象で、割引率は10%となります。
昭和56年6月1日以降では新耐震基準が設けられたため、これ以前の建物よりも地震に強いと判断されるためです。
利用例としては以下のようになります。
- 新築の家を購入した
- 築10年(建築年2010年)の中古住宅を購入した
一方、昭和56年5月31日以前に建築された中古物件を購入したなど新耐震基準以前の建物の場合、利用することができないので注意しましょう。
ただし、昭和56年5月31日以前に建築されたものでも、耐震診断や耐震改修を行い、基準を満たすことが証明されれば、「耐震診断割引」が適用されます。割引率は同じ10%です。築年数の古い家でも基準を満たせば割引が受けられるのです。
地震保険は建物の時価額に応じて補償される?築年数との関係は?
地震保険は、建物の時価額に応じて、補償額が左右されます。
なぜなら、地震保険の補償額は被災した時点の、建物の「価値」で決まるからです。
建物の被災した時点の「価値」を決めるのが「時価」になるのです。
しかし、そもそも「時価」の定義を知らないと、家の「価値」がどのように決まっているか理解ができませんよね。
そこで「時価」に関わる、基本情報についてわかりやすく解説していきます。
そもそも「時価額」とは?
時価と築年数の関係性とは?
時価額と地震保険の査定方法
それでは、1つずつ詳しく見ていきす。
そもそも「時価額」とは?
地震保険における「時価額」とは、保険対象となる建物・家財の現在の価値(評価額)を指します。時価額と同じように使われる用語として、「再調達価格」というものがありますが、
再調達価格
同じような建物・家財を再度建築・購入するとして必要な金額
時価額
再調達価格から、使用や経年劣化による消耗分を除いた金額
の関係性です。
ここで、「使用や経年劣化に伴う消耗分」とは、
年数が経てば経つほど消耗が大きくなってしまうので、
時価額はだんだんと小さくなっていきます。
時価は築年数が影響してしまう。
建物の使用年数が長いほど価格が下がる
時価を決めるうえで「築年数」は深く関係します。
時価と築年数の関係性を理解するには、
まずは「時価」がどのように決まっているか「計算式」を知る必要があります。
以下の式で表すと、
時価=同等の建物を再建築・再購入できる金額-消耗分の金額
当然、建物の使用年数が長ければ長いほど「消耗分の金額」が大きくなっていくので、
時価は低くなっていきます。
よって、築年数や居住年数が長い場合は、支払われる補償金の額が少なくなってしまう可能性があるということです。
ちなみに、木造の場合は築25年、マンションや戸建ての場合は築60年で、時価が2割ほどになります。
例えば、新築時に1,000万円の木造住宅なら、25年後には200万円ほどの価値にしかならないということです。
このように、築年数が古いと時価が下がるので、
普段支払う保険金の額が、万が一のときに下りる補償金の額を超えないか、
契約前によく考ておきましょう
地震保険の補償金額は時価額により査定される
地震保険の補償金額は、実際に地震被害にあった時点での
建物評価額(時価額)
被害の大きさに対する補償割合
の2つを元に金額を算出します。被害の大きさは、以下4段階に分かれていて、
被害の大きさ 地震保険金額に対する補償割合(時価が限度)
全損 全額
大半損 60%
小半損 30%
一部損 5%
被害状況に比例した保険金が支払われます。
ここで、注意すべきポイントは、
保険金額が満額もらえるわけではなく、「時価額が支払限度」ということです。
時価額は、建物が古くなれば価格も下がっていくものなので、築年数が大きくなればなるほど支払額は減少します。
例えば、
地震保険を1,000万円(建物)、500万円(家財)で加入
約12年後の時価が半減してしまった時点で地震被害にあった
地震被害は修復不可能(全損)の状態である
このようなケースの場合、
使用や経年劣化による消耗で建物の価値(時価額)が半減してしているため、時価額が支払上限となります。よって、補償金額は、建物が500万円、家財が250万円です。
全損だからといって、加入時の保険金額(契約金額)が満額もらえることを想定していると、
かなり目減りしてしまうのが分かるでしょう。
まとめ
今回は50年以上の家でも地震保険は使えることを説明していきましたが、
建物が古ければそれだけもらえる保険は減っていきます。
ですが、もらえないわけではないので、まずは申請することが大事です。
【台風救済センター】でも築が古い家の調査もしますが、満額おりる場合が多いです。
国の基準がいまいち曖昧なことや、保険会社によっても様々ですが、今まで減額されたり、申請したことない方はまずお気軽にご連絡ください。


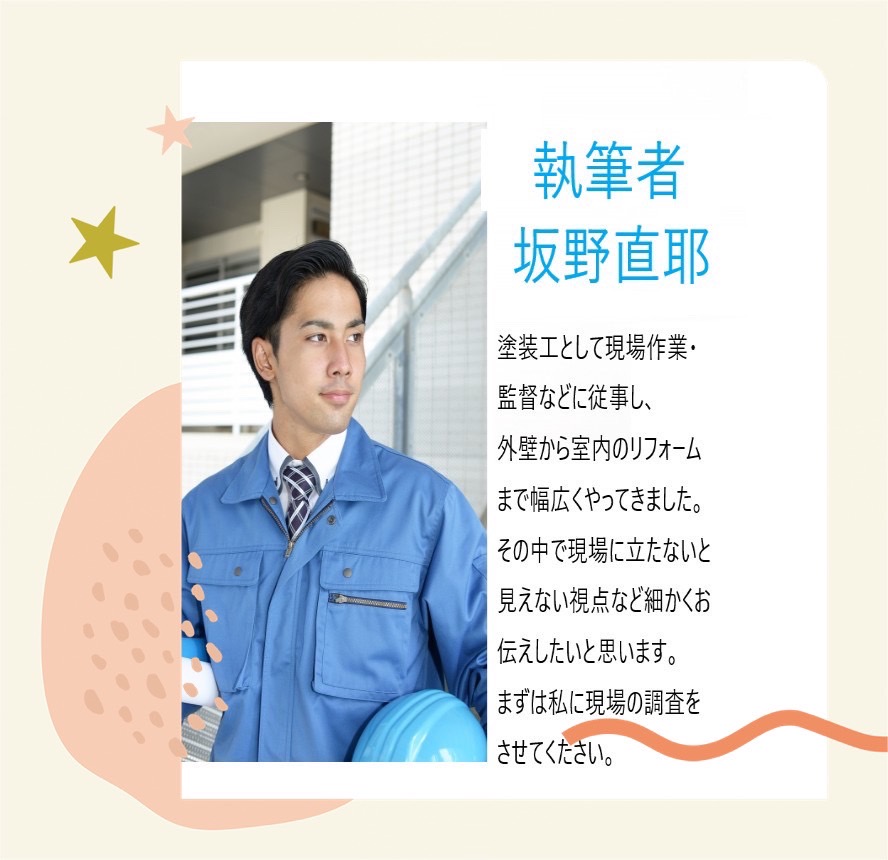
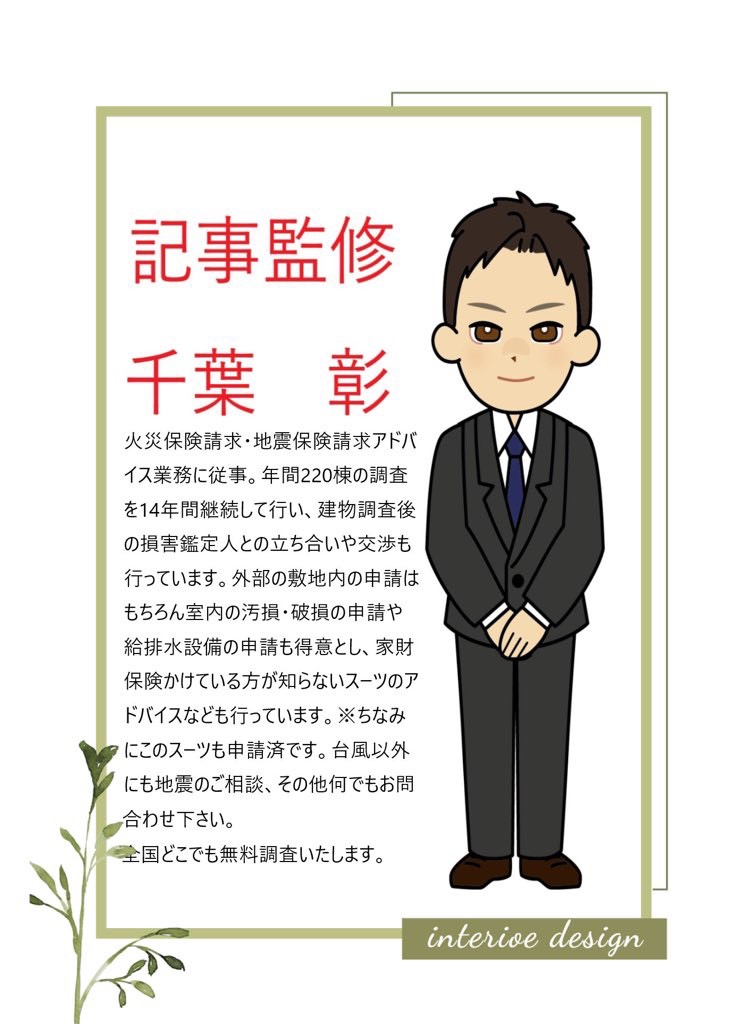
| 【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |
名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |