火災保険をご自身で請求できる方もいると思いますが、ほとんどの方は火災保険の請求の仕方や
請求の流れなど不明なことだらけではないでしょうか?
また、工事業者をどんなところにしたらよいのかなどもやはり悩んでしまい、
結果的に申請しなくなってしまうこともあります。
そういった思いの中、やっとで請求したけど、保険会社から経年劣化なので保険金の認定はできません。となるとかなりがっくりきてしまいますよね。
そして、それを言われたらやはりお客様だけでは、泣き寝入りする結果がほとんどです。
そういった経緯から火災保険サポート会社が増えているのも現状です。
保険会社からしたら、鬱陶しいと思いますが、保険を申請し、受け取る権利がある以上、
保険加入者には損してほしくありません。
今回は、「経年劣化で保険がおりなかった方や」「これから申請するけど不安な方」は最後まで
見てください。


目次
経年劣化とは
経年劣化
■年月の経過(経年)により色褪せが起きたり、製品が機能しなくなったりする(劣化)こと
■住宅に住む・利用する者の落ち度によらず、時間経過などにより自然に劣化してしまうこと
経年劣化は以上のように定義できます。
日当たり状況にもよりますが、外壁や壁紙の太陽光による「日焼け」は、2~3年で劣化の兆候が出てくることがあります。
また、和室の畳の色褪せや、外壁塗料のひび割れや室内の床の擦り傷、ワックスの剥がれ(重い物を移動させた時についた傷を除く)なども、
経年劣化です。
特に雨どいは熱被害といって経年劣化の一部として扱われてしまいます。



上記は熱被害ということで認定されませんでした。
なので、雨どいなどは台風後は定期的に調査し、記録を残しておくと、熱被害でないことが証明しやすくなります。
すべては保険会社OR鑑定会社判断
このような、ご自宅や建物などの経年劣化は火災保険の補償範囲ではないので、保険会社は自然災害による損害か、
経年劣化によるものか、その判断が微妙な場合は「経年劣化によるもの」と判断する傾向があります。
しかし火災保険は自然災害によるものはもちろん、
特約次第では水濡れによる被害についても補償範囲としているケースがあります。
(水濡れは経年劣化には含まれないので、火災保険の対象になる可能性が高くなります。)
では、経年劣化は絶対に火災保険は適用されないのでしょうか。
答えは×です。
実は、ある条件を満たせば火災保険が適用される可能性があります。
それは、火災保険の補償内容のひとつである「台風や強風などの風災による屋根に起きた被害」です。


雨漏りも火災保険対象になることもある
というのも屋根の損害の場合、経年劣化だと思われているもののほとんどが風災被害によるものだからです。
事実、屋根は経年劣化だけでは雨漏りはほとんど起きないといわれています。
どこかのタイミングで風災被害が出ているからこそ雨漏りが起きるのであって、風災被害である以上、その修繕は火災保険の補償範囲に含まれる可能性があります。
経年劣化と判断されないためには
まずあたりまえなのは、経年劣化は日がたつにつれて激しくなります。
そして、以前から被害あったのがわからない状態でいると基本的に保険会社も劣化
で話を終わらしてしまいます。なので、大事なことは
定期的に調査をし証拠として残しておくことが大事です。
【台風救済センター】でも定期的な無料調査大歓迎です。
こちらの記事も読んでみてください。↓
それは、
火災保険(地震保険)の時効が3年だからです。
保険の時効は、火災保険以外の保険も含め、保険法第95条に定められています。
その条項では、
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する
とあり、火災保険の請求権は原則3年で時効となります。
しかし保険法とは別に、各保険会社がそれぞれの請求期限を決めているケースもあり、1~2年に限定しているケースが多いです。
逆にその証拠さえあれば3年以上前の修繕工事でも台風が原因での屋根損害などがわかればお支払いになっております。
火災保険の約款の多くは、「被害が出た時はすぐに保険会社に連絡する」ことを求めています。
そのため、被害に遭った自然災害の日から少しでも過ぎてしまうと、火災保険は請求できないと思っている方も多いようです。
もちろん、火事や自然災害による被害箇所は、日が経つほど原因を正しく判断しづらくなるのも事実です。
被害原因を特定できず、それにより保険金が下りなくなることは避けなければなりません。


基準がないのか!?鑑定資格保有者の現状
損害保険鑑定人が被害状況を確認しレポートを作成している間に、
保険会社の事務方ではほかの作業を進めています。
契約内容の確認をしたり、契約されている建物の現在の評価額(時価)などをチェックしたりしています。
また、登記簿謄本上の所有者と契約上の所有者に間違いはないか、
免責金額はどのような契約になっているかなども確認します。
そして大事なのが、掛け金がしっかり支払われているかどうかです。
特に月払いの場合、連続して銀行引き落としが不能になっている状態が続いていると、保険金が支払われないことがあるので注意が必要です。
実際の損害額の査定は、損害保険鑑定人のレポートがベースになります。
そして、保険鑑定人の中にもはじめから保険をおろさないよう保険会社にいわれてきているパターンもあります。
鑑定会社にも大手や中小が存在する
最近の火災保険は、建物を新築するとした金額をベースに契約条項を制作し、その金額を上限にして損害額を支払うタイプが主流となっています。
建物については、現場検証をし、図面を引いて損害確認をしていくことから、専門的な方法で査定が行われます。
火災保険の契約者にとって、この場面で火災保険の認定が有利になるようにできることはありません。
とにかく、虚偽の報告・申請をしないこと、正しい理由があって申請することが当然大切です。
家財の査定方法とは
一方、家財の損害額の査定方法は建物の査定方法とは大きく異なります。
建物は、全焼したとしても構造・面積などから評価額を再計算することができます。
しかし家財の場合、「家財一式で数百万円」というような契約が主流で、それらが焼失してしまっては、どのような家財を所有していたか、知る由はありません。
そのため家財の被害申告については、火災保険の契約者が自己申告することになります。
家具であれば、居間にテーブルとソファがあって、書斎に書棚があって…などなど。
家電についても、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・パソコンなどが◯台ずつあって…などを申告。それらを積算して評価額のベースにします。
このように、家財については建物の査定と比較すると曖昧な部分があるようです。
台風救済センターが支持される理由
火災保険の補償対象となるにも関わらず、保険会社や保険代理店が加入者に案内をしないケースです。
例えば、台風による被害が出ていることを保険会社側が把握しているにも関わらず、
加入者に火災保険を申請する案内をしないで放置している事例などが挙げられます。
このような、火災保険でご自宅の屋根やカーポートなど、修繕ができるかどうかお金を残せるかどうかサービス提供しているのが
台風救済センターです。
自然災害による被害にも関わらず、経年劣化と判断されてしまっては、火災保険に加入している意味はなく、損ばかりする羽目に…。
被害に心当たりのある方は、まずは無料調査からはじめてみてはいかがでしょうか?
現場調査では登らずに高所カメラでの撮影も可能なので、壊された!!という心配もありません。
お気軽にお電話・メールお待ちしております。


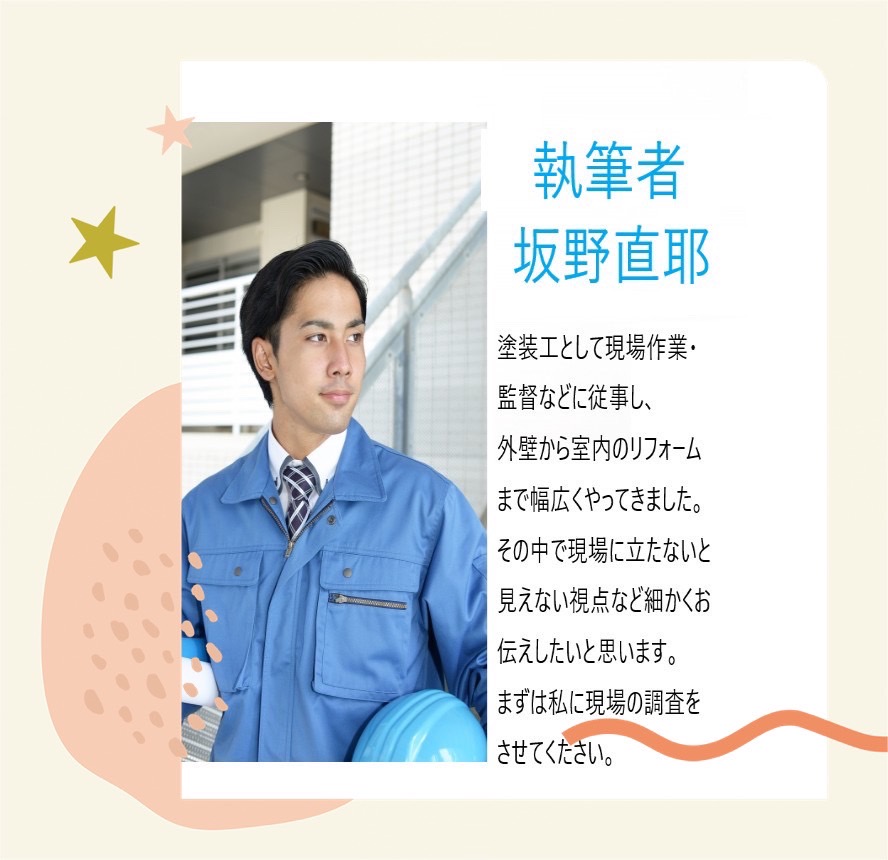
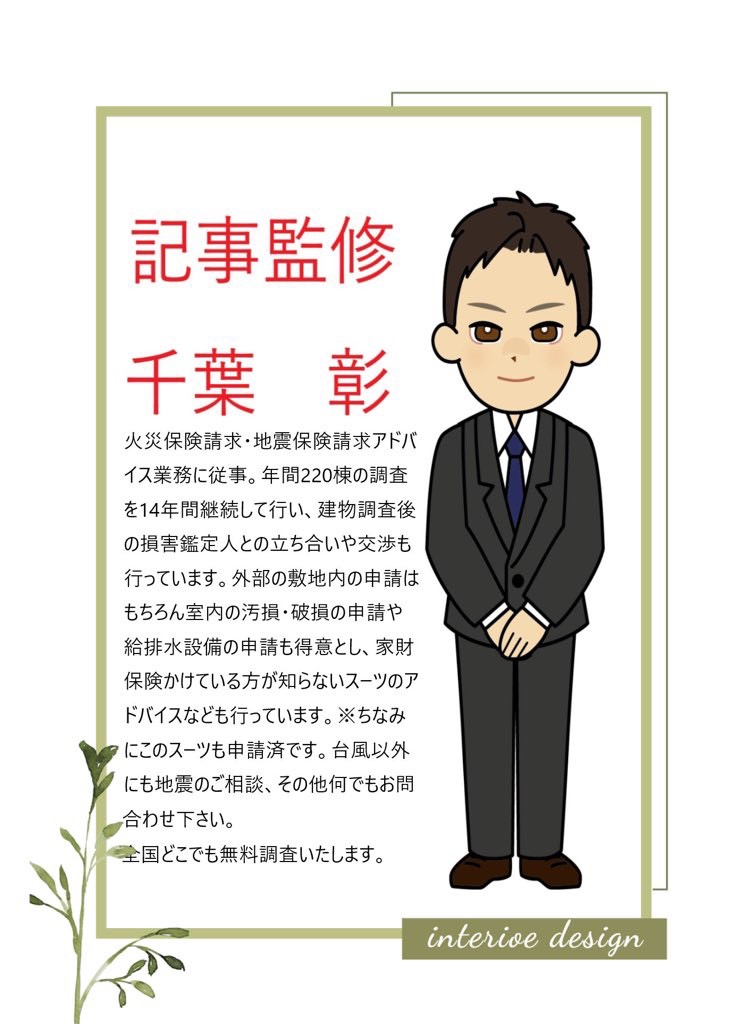
| 【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |
名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |



